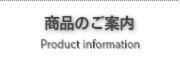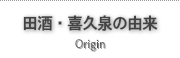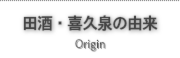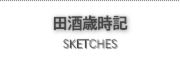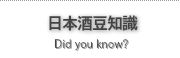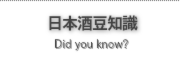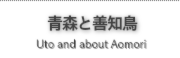昔から日本人に親しまれてきた日本酒には、現在までに積み重ねられてきた様々な歴史があります。今なお変わらぬ“しきたり ”や、時代の変遷ごとに洗練されてきた醸造方法、それらによって生み出された数々の特定名称酒の違い…ほんの少しの知識があるだけで、大好きな日本酒の楽しみ方は倍増するはずです。
ここではそんな単純な疑問や、酒造の文化・背景等をピックアップしていきたいと思います。
【あ〜】
青系酒140号
あおけいさけ140ごう
日本酒豆知識…「華想い」の項目を参照のこと。
秋上がり
あきあがり
寒造りで製造した清酒が、貯蔵することで一夏を越して秋になる頃にその酒質が向上していること意味する表現の一つです。
「秋上がり」は新酒のあらさがすっかり消えて、丸みが出て程よく熟成した飲み頃の酒とされており、この時期に「秋上がり」の酒を出荷することを「冷おろし」と呼んでいます。
また、逆に酒質が向上しなかった場合を「秋落ち」と言います。
アル添酒
あるてんしゅ
「アルコール添加清酒」の略称。増量のために水で薄めた醸造アルコールを添加したものは「普通酒」の部類に入るが、「特定名称清酒」では酒にすっきりとした風味とキレの良さを持たせるために、醪(もろみ)の段階から醸造アルコールが添加されていることが多い。
この場合、「特定名称清酒」に対する醸造アルコールの添加量は、白米重量の10%以下(95%アルコール換算による)でなければなりません。
エチルアルコール
えちるあるこーる
化学式:で示される飲料アルコールで、一般には「エタノール」と呼ばれています。
イモやトウモロコシ、サトウキビ、糖蜜等の澱粉質を多量に含んだ植物原料の発酵性糖類から酵母による発酵と蒸留によって生成されます。
日本酒においては、主にサトウキビから精製されたエチルアルコールを「醸造アルコール」として用いています。
滓
おり
「槽掛け(ふながけ)」<※ 田酒歳時記 参照>で上槽したての原酒は白濁しており、これを数日間静置することによって底部に白色の混濁物質が沈殿します。この沈殿物質を“滓”と呼んでいます。
また、底部に沈殿した滓から、上澄した部分を分離する作業を「滓引き」と呼んでいます。
【か〜】
寒造り
かんづくり
寒い季節に仕込みをすることを「寒造り」と呼んでいます。昔から年間の仕込みの中でも、冬から春の間の造りが最も良い出来であったことから、「寒造り」が酒造の主流となり広まっていったようです。
また、江戸時代において幕府の規制から「寒造り」以外困難な状況に措かれた事も一つの要因となっています。
生一本
きいっぽん
単一の酒造場のみで醸造した純米酒のみを「生一本」と表示することが出来ます。
自社醸造でも、別の製造場で造られた純米酒や、他社で造られた純米酒を混和したものには「生一本」の表示は出来ません。
生酛
きもと
「生酛」(きもと)は、乳酸菌の自然発酵を促し雑菌の繁殖を抑えるために 、蒸米、米麹、水を桶の中で数時間かけてすりつぶす “山卸し”(やまおろし)と呼ばれる非常に労力と時間のかかる作業を行う、昔ながらの伝統を受け継いだ酒母(酛)造りの方法です。
ちなみに「生酛法」には、上記の “山卸し”作業を廃した「山廃 」も含まれています。
酵母
こうぼ
いわゆる「イース ト」と呼ばれる微生物の一種のことの総称です。
酵母は「ビール酵母」や「ワイン酵母」といった使用目的に沿ってそれぞれに適したグループに分かれており、日本酒には「清酒酵母」と呼ばれるグループのものが使用されます。
「清酒酵母」は、麹(こうじ)によって糖化された米の糖分をアルコールと炭酸ガスに分解する働きがあり、味や香りなど清酒の重要な要素は酵母によって決定されると言っても過言ではありません。
その昔は酒蔵に付いた「家付き酵母」を醸造に用いていましたが、現在では(社) 日本醸造協会が純粋培養している優良酵母、いわゆる「協会酵母」を使用している蔵元が多く、またその他でも優良な酵母が作られています。
石
こく
体積を表す伝統的な単位。もともとは米穀を量るのに用いられた単位で、武家や大名の知行高として使われていた。酒造関係では、酒蔵の醸造規模を表すのに使われている。
ちなみに、一石は10斗(1斗は10升)で、180リットルに相当する。
甑倒し
こしきだおし
「寒造り」も終盤となり、最後の醪(もろみ)の仕込みに使う米を蒸し終える事を「甑倒し」と呼びます。
蒸米(ふかし)<※ 田酒歳時記 参照>をしていた甑を大釜から外し、それを横に倒して洗う様からこのように呼ばれるようになりました。
また、「甑倒し」当日は「蒸米」の無事終了を “酒造の祖神”に感謝し、蔵人によるお祝いが催されます。
古酒(長期熟成酒)
こしゅ
一般には、年月を経過し熟成した酒のことで、前年度あるいはそれ以前に造り、長期に貯蔵熟成された酒(長期熟成酒)のことを言います。
「古酒」と「新酒」の分け方は、酒造りが「寒造り」のみ行われていた頃は、「火入れ」を分かれ目にして上槽後火入れをしていない酒のことを「新酒」、火入れをし一定の貯蔵時間を経た酒のことを「古酒」と呼んでいました。
現在のように四季醸造など酒造りが長期化してからは、酒造季節である冬から春にかけての「寒造り」の時期を基準として、この造りの間に出来た酒のことを「新酒」、それ以前に造った(一夏越した)酒のことを「古酒」と呼んでいます。同じような考え方として、酒造年度を基準として「新酒」と「古酒」を分ける場合もあります。
古城錦
こじょうにしき
昭和43年に青森県農業試験場が、新潟から取り寄せた酒造好適米「五百万石」と青森県産米「青系50号」を人工交配させて開発・育成した酒造好適米品種です。
後に「古城錦」と命名された本品種は、青森県産初の酒造好適米奨励品種に推奨され、その評価は「五百万石」に勝るとも劣らぬものであると言われましたが、実状はほとんど酒造米として使用されることなく、採用年次は昭和55年までとわずか12年という短いものでした。
弊社では、今では“幻の米”とまで言われるようになった本品種「古城錦」の種籾をやっとの思いで探し出し、特定の農家に栽培を依頼することで復活させ、平成3年の造りから仕込みを開始して「田酒 古城乃錦」として地元向けに発売しています。
米麹
こめこうじ
古来より 日本や中国などでは、米や麦などの穀物にカビ類を繁殖させて “麹”(こうじ)を造り、清酒や味噌、醤油などの発酵工程に用いてきました。
この「麹造り」に必要不可欠なのがコウジカビで、冷ました蒸米に繁殖させたコウジカビは蒸米全体に菌糸を伸ばし、酵素を出してでんぷん質を分解して糖化させます。この状態を「米麹」(こめこうじ)と呼びます。
【さ〜】
酸敗
さんぱい
清酒の醪(もろみ)中に含まれる乳酸菌が増殖することによって、酸度が以上に高くなり、酒の香味が悪くなる事を言います。
醪を低温に保つ事によって“生酸菌”である乳酸菌の働きを不活性化させ、酸度の上昇を抑えることが可能ですが、中にはアルコール耐性があり低温にも強い乳酸菌が存在し、これらが「酸敗」や「腐造」といった現象を引き起こす要因ともなっています。
仕込み水
しこみすい
清酒醸造の “絶対条件”のひとつが、良質の「仕込み水」を使用することです。
鉄、マンガン、銅などの含有量の少ない透明なものが仕込みの好適水とされています。さらにカリウム、マグネシウム、燐酸が含まれていればなお良い「仕込み水」の条件を満たしていると言えます。
酒母:酛
しゅぼ:もと
清酒の「酒母」は「酛」(もと)とも呼ばれ、蒸米・米麹・仕込み水の混合物に 、優良な酵母を純粋培養したもので、 “生酛(きもと)法” と “速醸酛法”の二つに大別されます。
「生酛」は、乳酸菌の自然発酵を促し雑菌の繁殖を抑えるために、蒸米、米麹、水を桶の中で数時間かけてすりつぶす “山卸し”(やまおろし)と呼ばれる非常に労力と時間のかかる作業を行います。
ちなみに「生酛」の簡略型と言えるのが「山廃酛」です。
対して「速醸酛」は、化学生成された乳酸を添加してすみやかな発酵を促す醸造方法で「生酛」より早く安定した酒造りができます。
酒造好適米
しゅぞうこてきまい
酒造に適した 醸造用玄米(原料米)のこと。一般に大粒で溝が浅く、たんぱく質や脂肪が少ない、つまりは「心白」部分が大きいものほど優良な品種とされています。
代表格としては「山田錦」が有名です。ちなみに青森県産の代表的な酒造好適米として「華吹雪」、同じく県産の吟醸系醸造用酒米である「華想い」が挙げられます。
醸造アルコール
じょうぞうあるこーる
清酒の原料として使用されるアルコールの事です。「普通酒」における酒の増量や、「特定名称酒」では純米の持つ“重み”を抑え、風味を整えキレの良さを際立たせる等の目的で添加されます。
清酒の醸造アルコールは澱粉物質や含糖物質を発酵させ、蒸留することで得られるエチルアルコールであり、合成アルコールを一切使用しないことから、品質表示基準において「醸造アルコール」と呼称して明確に区別している。
杉玉:酒琳
すぎだま:さかばやし
酒蔵を通りかかったり、見学した事のある人なら見たことがあるはずのこの玉。酒蔵なら必ず軒先などに吊るしてある“杉玉”と呼ばれるものです。
古来、造り酒屋の看板として杉の葉を束ねて軒先に吊るし、その年の酒造りと酒造の神(松尾様)のご加護を願う風習がありました。これを“酒琳”(さかばやし)と言って、後に球状に造られたことから「杉玉」と言うようになったようです。
青々とした真新しい杉玉が吊るされると新酒が出来た目印となり、月日と共に色が褪せる様は酒の熟成度を表しているかのようでもあります。
精米:搗精
せいまい:とうせい
玄米の表層部や胚芽部分に含まれるタンパク質や脂肪、灰分は清酒の香味や色調を劣化させる成分が多く含まれ、醸造には大敵です。
清酒の風味を失わせないために 、これらの部分を取り除く作業を「精米」(搗精)と言います。
ちなみに 精米の程度を表す数値を「精米歩合」として表現しています。
精米歩合
せいまいぶあい
「精米歩合」とは、醸造に使われる原料米(酒造好適米)の表層部を取り 除く、「精米」の程度を表す数値(%)の事です。
精米歩合=白米重量÷玄米重量×100で表され、「精米歩合:40%」ということは、磨かれた白米の中心部分である『精米』が40%、糠(ぬか)として取り 除かれる周りの部分の『精白』が60%である事を意味しています。
上記のことからもわかるように 、世間では混同しがちな「精白歩合」(つきべり 率)の場合、糠が40%で 白米が60%という事になり、「精米歩合」と「精白歩合」とではその表す内容が逆となります。
一般的には “低精米歩合”、“高精白歩合”が酒の高品質の基準となります。
速醸酛
そくじょうもと
酒母(酛 )造りには、昔ながらの製法を受け継ぎ、乳酸菌の自然発酵を促す「生酛法」(きもとほう)と、市販の乳酸を使用する「速醸酛法」(そくじょうもとほう)に大別されます。
「速醸酛法」とは、自然の乳酸菌を使わず化学生成された薬品系乳酸を加えることで速成する酒母造りの方法で、「生酛法」による造りの半分以下の日数で、より早く安全な酒造りが出来るようになりました。
【た〜】
特定名称酒
とくていめいしょうしゅ
【特定名称酒一覧及び生産表】
|
[純米大吟醸酒]
|
原材料:米、米麹
精米歩合:50%以下
|
|---|---|
|
[大吟醸酒]
|
原材料:米、米麹、醸造用アルコール
精米歩合:50%以下
|
|
[純米吟醸]
|
原材料:米、米麹
精米歩合:60%以下
|
|
[吟醸酒]
|
原材料:米、米麹、醸造用アルコール
精米歩合:60%以下
|
|
[特別純米酒]
|
原材料:米、米麹
精米歩合:60%以下
|
|
[純米酒]
|
原材料:米・米麹
精米歩合:70%以下
|
|
[特別本醸造酒]
|
原材料:米、米麹、醸造アルコール
精米歩合:60%以下
|
|
[本醸造酒]
|
原材料:米、米麹、醸造アルコール
精米歩合:70%以下
|
清酒を大別する際、「特定名称酒」(特定名称清酒)と「普通酒」の二種類に別けられる。
特定名称酒は“高級酒”に該当し、これまでの一般清酒(普通酒)との差別化を計り、平成2年の法定化を経て原材料や製造方法が法律によって規制されている。
斗壜囲い
とびんがこい
「斗瓶取」(とびんとり)された雫酒を斗瓶で一定期間保存、滓引き及び熟成させる事を「斗瓶囲い」と呼びます。
「斗瓶囲い」は極端に数が少なく、その殆どが鑑評会用出品酒として用いられる貴重な酒です。
斗壜取り
とびんどり
最良の発酵状態を迎えた醪(もろみ)を酒袋に詰めて吊るす「袋取り」(または「首吊り」)と呼ばれる作業を経て、無加圧で自然に滴り落ちた酒の雫を斗瓶に集めることを「斗瓶取」(とびんとり)と言います。
ちなみに “斗瓶”とは、1斗(10升=約18リットル )の容量を持つ瓶のことを表しています。
【な〜】
生酒
なましゅ
「生酒」とは、「槽掛け」<※ 田酒歳時記 参照>と呼ばれる圧搾作業によって搾り出された清酒が、加熱処理を施されていない状態を指します。
貯蔵前と瓶詰前に行われる2度の火入れをしていないものを“本生”、生で貯蔵し瓶詰前だけに1度火入れしたものを“生貯蔵”、圧搾したあと一度火入れして貯蔵・出荷するものを“生詰”と呼んでいます。
いずれも2度火入れしたものに比べ、新鮮な風合いを残した口当りが特徴となります。
【は〜】
華想い:青系酒140号
はなおもい:あおけいしゅ140ごう
「華想い」は、国内で最も評価の高い酒造好適米「山田錦」に匹敵する県産米の育成を目標に開発が進められた青森県産品種です。
開花した「山田錦」に「華吹雪」の花粉をかけて人工交配し、品質が良く病気に強い品種を選定・改良することで誕生した本品種は、それまでの県産酒造好適米「華吹雪」では成し得なかった“大吟醸醸造酒米”として完成。「青系酒140号」の系統名を与えられ、平成14年に青森県奨励の酒造好適米に認定され「華想い」と命名されました。
弊社ではこの「華想い」を使用し、平成15年9月より 『純米大吟醸 百四拾 田酒』を発売しています。
華吹雪
はなふぶき
青森県農業試験場にて、「おくほまれ」と「ふ系103号」の人工交配によって開発・育成された酒造好適米品種のひとつです。
「青系酒97号」の系統名を与えられた本品種は、昭和61年に「華吹雪」と命名され、青森県の酒造好適米奨励品種に推奨されました。
耐冷性・耐倒伏性に優れ、短稈で多収性といった特徴を持ちますが、穂数が確保しにくく、大きな心白を持ちながらも高精白に耐えられないという弱点も持っています。しかしながら、総合的な酒造適正は安定した品種であるという評価を得ています。
火入れ
ひいれ
上槽された清酒の殺菌と酵素の働きを止めるため、60℃前後の熱を加える事によって低温殺菌します。これは「火落ち」を引き起こす乳酸菌の一種、火落菌を殺菌するのに非常に効果的で、新酒の貯蔵前の重要な作業です。
また、純米大吟醸や純米吟醸酒は、酒自体の香りや旨みをそのまま封じ込めるために瓶詰め後、特製の瓶燗機で64℃まで一本一本丁寧に加温し、瞬時に冷却する事でヒネを防ぎます。
火落ち
ひおち
清酒に火落菌が増殖することで起こる、清酒の白濁や酸敗といった「腐造」を助長する現象を言います。
火落菌は特殊な乳酸菌群で、アルコールに対する耐性があり、清酒中で容易に増殖します。しかし、熱には弱く、「火入れ」を行う事で容易に殺菌することが可能です。
老香
ひね
「老香」(ひねか)とは、清酒が長期熟成されたときに発生するにおいを指します。シェリー酒や老酒に代表される長期熟成酒にみられ、清酒の場合は老香よりも熟成香が好まれています。
老香発生には酒類に含まれる酵素が大きく影響しており、清酒の場合、低温貯蔵することで事前に老香発生を抑え熟成させます。
また生酒の段階において、酵素の働きが強かったために発生する独特のにおいを「生老香」(なまひねが)と呼んでいます。
冷やおろし
ひやおろし
元来、寒造りで醸造され貯蔵した清酒を、その温度と気温差が同じくらいになる秋に詰めて出荷することを言います。
昔は、貯蔵していた大桶から小樽に詰めて出荷する事から「冷卸し」と呼び、その風習が現在も形を変えて残っています。
この時期になると新酒のあらさがすっかり消え、丸みが出て程良く熟成した飲み頃の酒とされています
腐造
ふぞう
仕込み中の醪(もろみ)や、あるいは仕込み後の酒が酸度の上昇等によって酒質に変調をきたす事を言います。
腐造という現象は、清酒に限らず焼酎やワイン等の全ての醸造酒において起こり得る、最も気を付けなければいけないトラブルの代表格となっています。
この腐造を引き起こす「腐造乳酸菌」は、酸やアルコールへの耐性が強く、また一般の乳酸菌よりも低温に強いため、5~8℃という低温下の醪中でも生育して乳酸を生産するという特性を持っています。
普通酒
ふつうしゅ
普通酒とは、“特撰酒”や“上撰・佳撰”などと呼ばれる清酒やパック酒等の低価格の「アル添酒」を総称した「一般清酒」を指します。
一般清酒は、アルコール度数による規格によって審査される「級別制度」によって特級・1級・2級にランク分けされ、その酒税率の差で公定価格が決められていました。
しかし、昭和50年に始まった清酒の「原材料標示」と「製造方法標示」によって原料にこだわった清酒の商品化が増え、結果として「特定名称清酒」が誕生したことで、平成2年には従来の「級別制度」とは別の「特定名称清酒」に関する法定化が成立しました。その影響で従来の「級別制度」は平成4年に廃止されています。
現在では「特定名称清酒」の限度外で醸造される清酒を総称して「普通酒」と呼んでいます。
【ま〜】
松尾様
まつおさま 【松尾大社】
【松尾大社】
「松尾様」とは、酒蔵で祀られているいわゆる“酒造りの神様”のことです。
蔵人が奉る「松尾様」と称される神は女神とされており、古来より酒蔵が“女人禁制”とされてきたのは、蔵に女性が入ると「松尾様」がヤキモチを焼いて酒を腐らせてしまうという言い伝えによるとも一説では言われています。
「松尾様」は“日本酒醸造の祖神”として全国の酒造蔵より崇敬を受けている京都嵐山に鎮座する「松尾大社」の尊称で、平安期に大陸より持ち込んだ新しい醸造技術を以って現代の清酒醸造の基礎を確立した秦氏の氏神を、太秦「大酒神社」より摂社として奉祀したことにより、本来の御祭神である“大山咋神”(おおやまくいのかみ)と呼ばれる農耕信仰の守護神や、宗像三女神の一人である“市寸島比売命”(いちきしまひめのみこと)と呼ばれる航海の女神と混同して蔵人が信仰したことから「松尾様」なる“酒の女神”となったと思われます。
ちなみに「松尾大社」の他にも、全国の酒造家より“酒造の祖神”として幅広い信仰を受けている奈良の「三輪明神」があります。
酒蔵ではその年の酒造りに、“酒造の神”のご加護を願う風習として、杉の葉を束ね球状に造った“杉玉”(酒琳=さかばやし)を軒先に吊るします。
醪
もろみ
酒類になる前段階のものを指して醪(もろみ)と呼んでいます。
酒母に水、麹、蒸米を3回に分けて仕込んだもので、糖化と発酵を進めて清酒の母体となるものを言います。
【や〜】
山田錦
やまだにしき
現在の清酒醸造において、国内の数ある酒造好適米の中で最も評価の高い品種が「山田錦」です。
原産は兵庫県で、「山田穂」と「短稈渡船」の人工交配によって誕生した本品種は、大粒の玄米ながらたんぱく質や脂肪が少なく、それでいて心白が多く、また糖化に優れているという酒造好適米における必須条件を満たした極良質となっています。
しかしながら、中山間地等の粘質土壌や盆地特有の昼夜の大きな寒暖差を要するなど育成条件が限定され、また粒の大きさと長稈の関係から耐倒伏性に弱く、いもち病等の病虫害に弱いなど育成が難しい事から全国的にも生産量は多くありません。
山廃酛
やまはいもと
「山廃」とは、“山卸廃止酛 (やまおろしはいしもと)”の略で、「生酛 」(きもと)において行われる伝統的な「酒母造り」の作業である「山卸し」(やまおろし)を廃した、いわゆる「生酛」の簡略型といえます。
より自然の力で乳酸菌の自然発酵を行いますが、「生酛 」同様 “腐造”の危険性があり、その管理と育成には大変な苦労を要します。